スキーシーズン以外の経営がスキー場再生のカギとなる

鈴木:スキー場の大きな課題として、冬以外に事業がなかったことがあげられます。しかし、実際にその地域で暮らしてみると、グリーンシーズンにもそれぞれの地域の魅力がたくさんあることに気がつきます。例えば長野県の鹿島槍には、数百人が宿泊できるスキーヤーズベッドがありました。これを活用し、年々増えていたキッズキャンプイベントの企画や、トライアスロン競技者の合宿施設としての営業も始めました。竜王では、日本で最大のロープウェイというハードの強みと、山頂エリアならではの絶景や景色といった自然を最大限活用し、ソラテラス事業を始めました。標高約1800mの山頂エリアに設置されたテラスで、美しい雲海や夕焼けをゆったりと楽しめます。また、ソラテラスのすぐ隣のレストランの大幅なリニューアルと、メニューも一新、美味しい食事やコーヒーを堪能いただけるようになったことで非常に多くの女性のお客様にご来場いただけるようになりました。また、白馬岩岳は、グリーンシーズンに200万輪が咲き誇る広大なゆり園を散策できることで人気を博していますが、あらたにマウンテンバイクのフィールドをオープンし、毎年コースを新設することで年々お客様が増えてきました。こんなふうに、既存のハードやそれぞれの山がもつ魅力を最大限活かし、グリーンシーズン事業にも注力しています。収益が向上するだけではなく、冬だけのパート社員から正社員を増やすこともできるようになってきたのです。

鈴木:日本スキー場開発の創業メンバーは、スキーが大好きな人ばかり。「毎年スキーに行かない人の気持ちが分からない」と言うのです。でも、私はスキーに行かない人の気持ちもよく分かります(笑)。だからこそ、客観的にスキー場のサービスを判断し、改善を進めることができたと思います。一方で、私は地域創生に非常に興味がありました。その地域にしかない物を見つけ出し、世間に広める事でその地域の価値を高められればと思っています。スキー場自体も良くしていき有名にしていくことは勿論頑張っていくのですが、その地域がさらに元気になっていくお手伝いもしていきたいと考えています。岐阜県の、めいほうというスキー場の地元では明宝ハムという非常に有名なハムの他にも美味しいお米があることを見つけました。また、群馬県の川場スキー場がある川場村では何度もお米のコンクールで金賞に輝いた雪ほたかなど素晴らしい特産品があります。めいほうと川場の道の駅では、こういった食材を活用し、おにぎり屋を私たちが運営しています。 日本スキー場開発というよりは、スキー場や地域の方たちが主役になって頂くことを大切にしています。すでに鹿島槍と川場スキー場、めいほうスキー場では、地元の方に代表を任せています。私たちと一緒にスキー場経営を行う中で、経営のノウハウを吸収して頂き、いずれは地元の方に経営者になって頂く。地域の方にとっても、その方が喜ばれると思いますし、経営できる人財が地元に産まれていく事は、その地域が元気になっていくことにも繋がっていくと思っています。長期的な目線をしっかりともち、地域へのサポートと基幹事業であるスキー場をハードとソフト、両面でリノベーションをしていき、20年、30年後を見据えてさらに良い未来を、地域と一緒になって創っていきます。

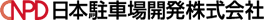






 スポーツ事業の取り組みについて
スポーツ事業の取り組みについて

 日本スキー場開発株式会社
日本スキー場開発株式会社
 ハクババレー
ハクババレー 白馬岩岳マウンテンリゾート
白馬岩岳マウンテンリゾート ソラテラス
ソラテラス 日本テーマパーク開発株式会社
日本テーマパーク開発株式会社 那須ハイランドパーク
那須ハイランドパーク 那須高原りんどう湖ファミリー牧場
那須高原りんどう湖ファミリー牧場







